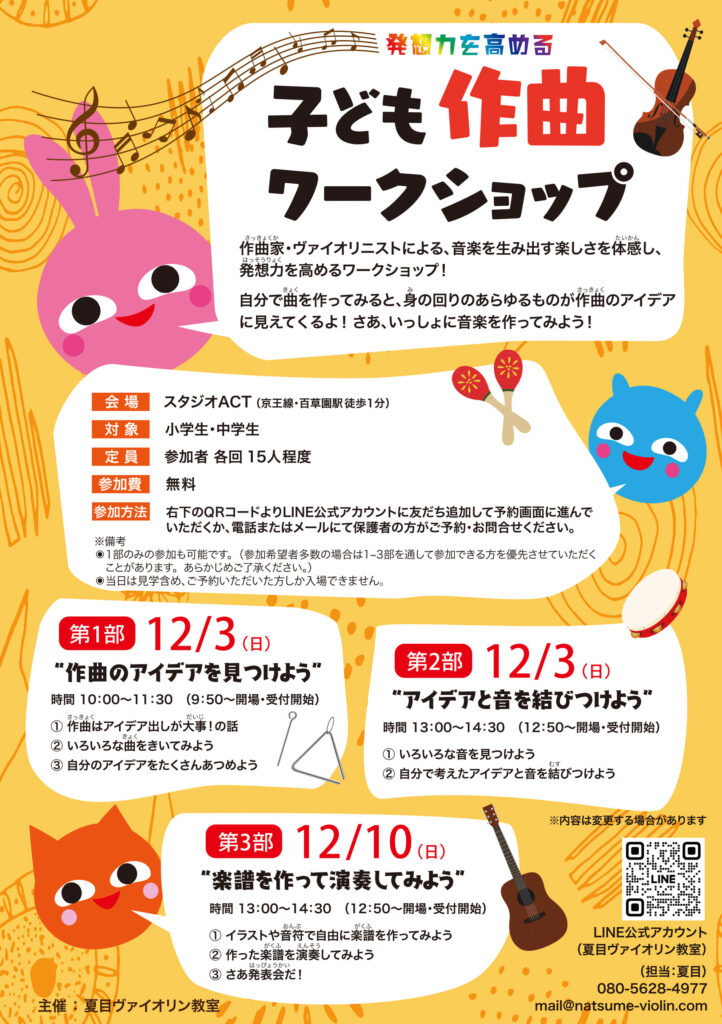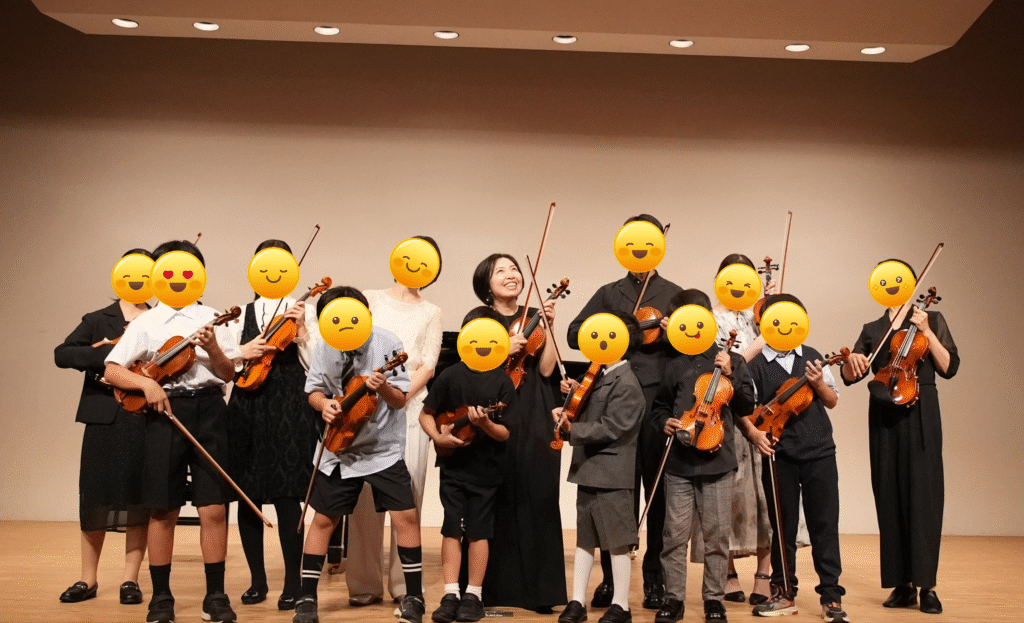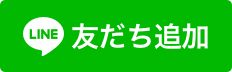絶対音感について、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
なんとなく、絶対音感に憧れを持っていて、プロの音楽家ならは持っているべきスキルのように思われている方が多いような気がします。
最初にお伝えしますが、私は絶対音感を持ってはいません。
学生時代は絶対音感を持っていることが良しとされる環境でしたので、本当に苦労しました。ですから、当時は絶対音感を持つクラスメイトたちを羨ましく感じていました。
でも今では、この音感が身につかなくて本当に良かったと感じています。
なぜなら、私は絶対音感というものは、この現代の周波数442Hz(あるいは440Hz)で調律されたピアノでのみ通用する音感であり、そこに付随する音楽業界内で、速く譜読みをしたり、速く楽譜を書いたりする必要がある演奏家や作曲家というコストパフォーマンスを求められる音楽家にのみ、メリットがあるものだと思うようになったからです。
絶対音感というものは、音楽要素の中の「音の高さ」の認識をかなり単純化させたものです。そしてそれは、おそらく、脳が自分の意思とは関係なく、効率化のために音程を単純化して処理しているのだと思います。それゆえに、音程の形をはっきりくっきりさせて「曲」として認識しやすくできる反面、音楽のもつ重要な音程に関わる要素は切り捨ててしまっているのだと思います。
絶対音感のある友人のピアニストたちは、ピアノの鍵盤では表現のできない間の音程を聴くと「ズレた音程で気持ちが悪い」と感じると嘆いていました。でも、世界には様々な音程感覚をもつ音楽が存在しているので、あまりに強い絶対音感の持ち主は、そういう音楽を聴く楽しみも捨ててしまうことになっているのではないかと私は考えています。
音程はピアノの鍵盤から外れているところにも「連続的に」存在しています。音と音との距離や空間、関係性を表現するために音程を意図的に高め低めに位置させることは音楽を生み出す側の意識としてはとても重要ですし、それは日々、音程に向き合っているヴァイオリン弾きには当たり前のものです。
ヴァイオリンは、音程を自分の意図した場所で区切ったり、曖昧にすることもできる楽器です。調弦一つとっても、頭の中にある正しい音程に合わせる、ということではなく、基準とする周波数が常に変わることを前提に行なっているので、基準にする音の波形と重ねる音の波形がぶつかる時に発生する音の震え具合を聴き分けています。そもそも、4本の弦の音程はしょっちゅう狂いますし、一緒に演奏している相手の弦が狂うこともあります。
また、演奏する調によっても同じ階名の音でも高めに弾いたり、低めに弾いたりするのです。たとえば、「ドレミファソラシド」のハ長調では、ヴァイオリンでは「シ」の音程をものすごく高くします。それがヴァイオリン弾きには心地よい音程なのです。でも、ピアノの鍵盤の「シ」は、固定されているので、ヴァイオリン弾きにとっては、かなり低く感じてしまいます。ちなみに、「ラシド#レミファ#ソ#ラ」のイ長調の「シ」はピアノの鍵盤の音程でも違和感はありませんが、この調の場合は「ソ#」を高くした方が心地良いです。
なんにせよ正しいと感じる音程は一定ではなく、常に変わるというのがヴァイオリン弾きの感覚なものですから、限られた職業の方以外は、絶対音感がない方がメリットが多いのではないかと私は考えています。
以上、私の個人的な感想・意見でした。